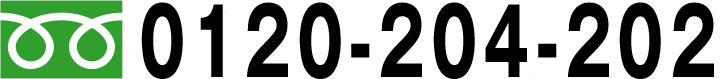50年以上の耐久性を誇る丈夫な日本瓦にも、適切なメンテナンスが必要です。
本記事では、軽微な劣化から重度な損傷まで、症状別の修理方法を詳しく解説します。
DIYで対応できるものから専門業者への依頼が必要なものまで、正しい判断基準をお伝えします。
自分で修理できる症状と業者に頼むべき症状
日本瓦は症状によって、DIYで修理ができる場合とプロの業者に依頼すべき場合があります。
DIY可能な軽微な劣化症状
軽微な劣化であれば、安全を確保した上でDIY修理が可能です。
瓦のわずかなズレ直し
- 1~2枚程度の軽微なズレ
- 平屋や2階建ての軒先付近
- 手の届く範囲での作業
小さなひび割れの応急処置
- 髪の毛程度の細いひび
- 防水テープでの一時的な補修
- 雨漏りが発生していない段階
清掃やコケ除去
- 瓦表面の汚れやコケ
- 高圧洗浄機を使用した清掃
- 滑りにくい安全靴での作業
ただし、高所作業は非常に危険です。
必ず安全帯や滑り止めを使用し、天候の良い日に行いましょう。
専門業者への依頼が必須な重度の劣化症状
以下の症状は専門技術が必要なため、必ず業者に依頼してください。
瓦の大きな割れや欠け
- 瓦の3分の1以上が損傷
- 複数枚の瓦に影響
- 構造的な強度低下の可能性
棟瓦の崩れや大幅なズレ
- 既存の棟瓦を一度解体し、再度積み直す「棟の取り直し工事」が必要
- 耐震性能の向上が求められる
- 専用工具と高度な技術が必要
雨漏りが発生している場合
- 防水シート(ルーフィング)の損傷可能性
- 屋根下地の腐食リスク
- 建物構造への影響
漆喰の大規模な剥がれ
- 棟部分の広範囲な補修
- 専用材料と施工技術が必要
- 防水性能の確保が重要
屋根の修理はプロでも危険が多い高度な作業になるため、素人が行うことは避けた方が無難とされています。
日本瓦の修理方法
日本瓦の修理には、軽微な補修から大規模な工事まで複数の方法があります。
損傷の程度や予算、工期などを総合的に考慮して最適な修理方法を選択することが重要です。
ここでは5つの主要な修理方法について、それぞれの特徴とメリット・デメリットを詳しく解説します。
漆喰の補修
瓦屋根の棟(頂上部分)や瓦の隙間を埋めている漆喰は、瓦の固定や雨水の浸入を防ぐ重要な役割を担っています。 経年劣化によりひび割れや剥がれが生じると、そこから雨水が浸入し、内部の葺き土(ふきつち)が流出することで、瓦のズレや棟の崩壊につながる恐れがあります。
補修では、劣化した古い漆喰を取り除き、新しい漆喰を塗り直す「詰め直し」が基本的な方法です。劣化が軽微な場合は部分的な補修も可能ですが、放置するとより大規模な修理が必要となるため、定期的な点検と早めの補修が大切です。
メリット
- 比較的費用を抑えられる修理方法
- 定期的な補修により防水性能を維持できる
- 工期が短く、部分的な補修なら1~2日で完了
- 既存の瓦を活用できるため、材料費も抑制可能
- スレート瓦や金属製屋根材とは異なる日本瓦特有の補修
デメリット
- 下地の劣化が進んでいる場合、補修効果が限定的
- 再発リスクが高く、数年後の再補修が必要になることも
- 施工技術により仕上がりに差が生じやすい
瓦の交換
台風による飛来物や経年劣化により、瓦にひび割れ、欠け、ズレが生じることがあります。日本瓦の屋根は、損傷した瓦のみを一枚から交換できるのが利点です。
修理は、まず周囲の瓦を慎重に持ち上げ、割れた瓦を取り除きます。次に新しい瓦を差し込み、釘やビスでしっかりと固定。部分的な補修で済むため、費用を抑えやすい修理方法ですが、廃盤になっている瓦の場合は、似た形状のものを探すか、他の部分から状態の良い瓦を移動させて対応することもあります。
メリット
- 損傷した瓦のみを交換する経済的な修理方法
- 瓦一枚から交換できる利点(金属屋根やスレートとは異なる)
- 既存の屋根構造を維持しながら修理可能
- 同じ種類の瓦を使用すれば見た目も統一される
- 工期が短く、ピンポイントでの対応が可能
デメリット
- 古い瓦は製造中止になっているケースが多い
- 色合いや質感の微妙な違いが目立つ可能性がある
- 一枚だけの交換では根本解決にならない場合も
棟瓦の取り直し
屋根の頂上にある棟瓦は、漆喰の劣化や内部の葺き土の流出により、歪んだり崩れたりすることがあります。 このような状態を放置すると、雨漏りや強風による棟の倒壊といった深刻な事態を招く危険性があります。
棟瓦の取り直し工事では、一度棟瓦をすべて解体・撤去します。 その後、劣化した漆喰や土を取り除き、必要であれば補強金具などを設置した上で、再度瓦を積み直し、漆喰で固定します。 これにより、棟の強度と防水性が回復します。
メリット
- 耐震性能の向上が期待できる修理方法
- 既存瓦の再利用により材料費を削減可能
- 屋根全体の構造強化につながる
- 長期的な安全性確保が可能
- 台風や地震対策として一定の効果がある
デメリット
- 工事費用が高額になりがち
- 工期が長く、天候に左右されやすい
- 専門技術が必要で、業者選択が重要
- 「葺き直し」「葺き替え」ほどの抜本的対策ではない
葺き直し
葺き直しは、既存の瓦を一度すべて剥がし、瓦の下にある防水シート(ルーフィング)や野地板といった下地を補修・交換した後、剥がした瓦を再利用して葺き直す工法です。瓦自体に問題はないものの、下地の耐用年数(約20~30年)が過ぎ、雨漏りの心配がある場合などに行われます。
瓦を再利用するため、屋根の外観を変えずに済み、新しい屋根材を購入する費用がかからないというメリットがあります。ただし、瓦を一枚ずつ丁寧に剥がして再度葺くため、手間のかかる工事です。
メリット
- 瓦が破損していなければ再利用可能な経済的工法
- 既存瓦を活用するため材料費を大幅削減
- 防水シート(ルーフィング)の交換により防水性能が向上
- 屋根下地の補強も同時に実施可能
- 葺き替えより費用を抑えられる
デメリット
- 100~180万円程度の費用が必要
- 既存瓦の再利用のため、一部破損瓦の交換が必要な場合も
- 工期が長く、天候による作業中断リスクがある
- 瓦の劣化状況によっては適用できない
葺き替え
葺き替えは、既存の瓦と下地をすべて撤去し、全く新しい屋根材と下地に交換する全面リフォームです。 瓦の劣化が激しい場合や、雨漏りが深刻で下地の腐食が進んでいる場合に行われます。
また、重い瓦屋根から軽量な金属屋根などに変更することで、建物の耐震性を向上させる目的でも選ばれます。工事は大掛かりになり、費用も高くなりますが、屋根の機能が新築同様に回復し、建物の寿命を延ばすことにつながります。
メリット
- 屋根全体を新しくする最も確実な修理方法
- 新しい屋根材により長期的な安心が得られる
- 最新の防水技術や耐震技術を導入可能
- 屋根材の変更により軽量化も可能
- 建物全体の資産価値向上につながる
デメリット
- 140~200万円という高額な費用が必要
- 全屋根材を撤去するため、廃材処分費も発生
- 工期が最も長く、2~4週間程度が一般的
- 仮住まいの検討が必要になる場合もある
- 近隣への騒音や粉塵対策が必要
修理を放置した場合の3つのリスク
「少しのひび割れだから」「まだ雨漏りしていないから」といった自己判断で屋根の劣化を放置すると、後々、大規模な修繕が必要となるばかりか、住まい全体の寿命を縮める事態に発展する可能性があります。
修理を先延ばしにすることで生じる、3つの深刻なリスクについて詳しく解説します。
①雨漏りの発生と拡大
瓦のひび割れやズレ、漆喰の剥がれといった初期症状を放置すると、そこが雨水の浸入口となります。はじめは僅かな浸水でも、時間と共に屋根内部で被害が静かに進行し、気づいた時には深刻な状況になっているケースが少なくありません。
初期段階
瓦の隙間から雨水が浸入し、屋根の防水の要である防水シート(ルーフィング)を劣化させます。
棟瓦の漆喰が崩れると、内部の葺き土が雨水で流れ出し、瓦の固定力を弱めます。
中期段階
劣化した防水シートが破れ、下地である野地板にまで雨水が到達。天井や壁にシミが現れ始め、カビが発生しやすくなります。
末期段階
室内への雨漏りが始まり、家具や家電製品に直接的な被害を及ぼします。
カビの胞子が室内に飛散し、アレルギーや喘息といった健康被害を引き起こす可能性も。また、漏電による火災のリスクも高まります。
②屋根下地の腐食
継続的な雨水の浸入は、屋根の表面だけでなく、建物を支える重要な構造部分を蝕んでいきます。
屋根下地の腐食
雨水によって常に湿った状態が続くと、屋根材を支える野地板や垂木といった木材が腐食し始めます。
下地が腐食すると、瓦を固定する力が失われ、強風や地震の際に瓦がズレたり、落下したりする危険性が増大してしまうのです。
構造強度の低下
腐食は柱や梁など、建物の骨格にまで及び、家全体の耐久性を著しく低下させます。
湿った木材はシロアリの格好の餌食となり、被害がさらに深刻化する恐れがあります。 最悪の場合、地震などで家屋が倒壊するリスクも否定できません。
③修理費用の高額化
屋根の修理は、対応が早ければ早いほど費用を抑えることができます。しかし 放置して被害が拡大すれば、修理箇所が増え、工事も大掛かりになるため、費用は雪だるま式に膨れ上がるでしょう。
まとめ
日本瓦は50年以上の耐久性を持つ優秀な屋根材ですが、適切なメンテナンスは欠かせません。
軽微な症状なら自分で対応できる場合もありますが、安全面を最優先に考えることが重要です。
修理を放置すると雨漏りや下地腐食、費用の高額化というリスクが待っています。
定期点検を怠らず、異常を発見したら早めに専門業者に相談しましょう。
適切な修理により、日本瓦の持つ優れた性能を長期間維持することができます。