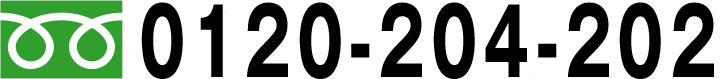京都市にお住まいで、自宅の耐震性に不安を感じている方、特に重い瓦屋根の軽量化リフォームを検討している方へ、「まちの匠・ぷらす」京町家・木造住宅 耐震・防火改修支援事業をご紹介します。
この制度は、木造住宅の耐震化を支援し、市民が安心して暮らせる住環境を実現することを目的としており、2025年度には制度の一部見直しも行われ、より利用しやすくなっています。
本記事では、京都市の屋根軽量化補助金の具体的な内容、適用条件、申請手続き、さらには他の耐震リフォーム補助金との併用について、詳しく解説します。
京都市の屋根軽量化補助金は最大60万円
京都市が提供する「まちの匠・ぷらす」事業には、「簡易改修」として屋根の軽量化工事が含まれており、補助金の対象となります。この補助金は、最大で60万円が交付される可能性があります。
補助金の詳細な金額と補助率
屋根の軽量化工事は「簡易改修」の「屋根型」に分類され、以下の補助限度額が設定されています。
- 京町家の場合: 最大 60万円
- 一般的な木造住宅の場合: 最大 40万円
補助金額は、補助対象費用の4/5または上記の補助限度額のいずれか少ない方の額となります。
補助対象となる屋根軽量化工事の内容
屋根の軽量化は、「屋根を軽くする工事」として定義されています。屋根が重いほど、地震が発生した際の建物の揺れが大きくなるため、軽い屋根材に替えることで揺れを小さくし、建物が倒壊する可能性を低減させることができます。
具体的には、既に軽量化されている部分を除き、下屋(げや)も含めた屋根の全て(庇を除く)を軽量化する工事が対象です。例えば、非常に重い土葺(どぶき)瓦から桟瓦葺(さんかわらぶき)や金属板などの軽い屋根材への葺き替えなどが該当します。
補助金を受け取るための必須適用条件
補助金を利用するには、対象となる住宅や申請者、工事内容に特定の条件が設けられています。
対象となる住宅の条件
補助の対象となる建築物は、以下の全てを満たす必要があります。
- 京都市内にある木造の一戸建て住宅、長屋、または共同住宅
- 店舗等を兼ねる併用住宅も、居住部分の床面積が延べ面積の1/2以上であれば対象
- 空き家の場合でも、工事完了後に速やかに住宅として利用する予定であれば対象
- 建築年次
- 一般的な木造住宅: 昭和56年(1981年)5月31日以前に着工されたもの
- 京町家: 昭和25年(1950年)11月22日以前に着工されたもの
対象となる申請者の条件
補助金の申請者は、以下のいずれかに該当する方です。
- 対象建築物の所有者またはその二親等内の親族
- 対象建築物の居住者またはその二親等内の親族
- 対象建築物の居住予定者
重要な注意点
- 所有者以外が申請する場合や、複数の所有者がいる場合は、関係者全員の同意が必要です。
- 賃借人がいる場合は、賃借人全員の同意を得るか、十分周知した上で反対の意思を示す者がいないことを確認してください。
- 工事の施工者は、京都市内の事業者である必要があります。特に、簡易改修(屋根軽量化を含む)や防火改修を行う場合(本格改修と併せて実施する場合を除く)は、京都市内に本店または主たる事務所を置く事業者が請負人または下請負人として施工することが条件です。
事前の無料耐震診断の必要性
屋根の軽量化は「簡易改修」に該当するため、本格改修のように改修前後の耐震診断は必須ではありません。
しかし、制度には「耐震診断をして金額アップ!」という記述があり、京都市では無料で建築の専門家に耐震に関する悩みを相談できる「耐震相談会」も実施しています。耐震診断を行うことで、建物の総合的な耐震性能を把握し、より効果的な改修計画を立てることが可能です。
補助金申請の4ステップと必要書類
補助金申請の手続きは、以下の4つのステップで進められます。
ステップ1 事前相談と事業者選定
まず、京安心すまいセンターに電話で事前予約をして相談することをお勧めします。ここでは、補助金制度に関する詳しい説明を受けられるほか、専門知識を持つ団体を紹介してもらうことも可能です。 工事契約や工事の着工は、必ず交付決定通知後に行ってください。交付決定前に着工している建物は補助の対象外となります。
ステップ2 交付申請書の提出
設計または工事に着手する前に、交付申請書類を提出します。
- 申請期間
令和7年4月14日(月)から令和8年1月31日(土)まで。ただし、予算がなくなり次第受付は終了しますので、早めの申請が推奨されます。 - 提出方法
京安心すまいセンターの窓口に持参するか、郵送(レターパック等)で提出します。郵送の場合は、「まちの匠申請書在中」と記載し、必ず書類のコピーを手元に残してください。
主な必要書類
- 交付申請書(第1号様式)
- 補助金額算出書
- 付近見取図(所在地が確認できる地図)
- 建築時期を確認できる書類(登記事項証明書、検査済証など)
- 補助対象者であることを確認できる書類(登記事項証明書、住民票の写しなど)
- 建物の全景写真、現状図面
その他、必要に応じて追加書類が求められる場合があります。
※感震ブレーカーの設置のみを行う場合は、申請書類の一部が省略可能です。
ステップ3 工事着工と完了報告
交付決定通知書を受け取った後、工事に着手できます。工事の内容や費用に変更が生じ、交付予定額が変わる場合は、該当する工事を行う前に変更申請が必要です。軽微な変更(工事種別ごとの交付予定額に変更を生じない工事内容や費用の変更、工事施工者や申請者の住所の変更など)は、完了報告時にまとめて提出できます。
- 完了報告期限:令和8年3月1日(日)まで
工事が完了したら、速やかに完了報告を行ってください。
主な必要書類
- 実績報告書(第7号様式)
- 請負契約書の写し(交付決定通知日以後の契約日が記載されているもの)
- 領収書の写し
- 施工状況を示す写真および写真撮影方向図(工事前、工事中、工事完了後の写真が必要)
- その他、変更内容に応じた書類など
工事の適切性を確認するため、工事途中に現場検査が行われる場合があります。検査の連絡があった場合は、仕上げ材などで施工が隠れる前に希望日時を京安心すまいセンターに伝え、申請者または代理人の立ち会いが必要です。
ステップ4 補助金の請求と受領
完了報告書類の提出後、審査を経て交付額が決定されます。その後、補助金請求書(第8号様式)を提出することで、補助金が振り込まれます。
代理受領制度とは本格改修の場合に利用できる制度で、工事費と補助金の差額を用意すれば、申請者が一旦全額を立て替える必要がなく、工事施工者が補助金を代理で受け取ることができます。これにより、一時的な費用負担を軽減できます。簡易改修のみの場合は、申請者が補助金を直接受け取ります。
屋根軽量化と併用できる京都市の耐震リフォーム補助金
京都市の「まちの匠・ぷらす」事業では、屋根軽量化(簡易改修)以外にも、さまざまな耐震・防火改修工事が補助対象となっています。これらを組み合わせることで、より総合的な安全性の向上が期待できます。
耐震改修工事への補助制度(本格改修)
本格改修は、耐震診断に基づいて建物の耐震性能を向上させる工事が対象です。改修前後の耐震診断が必須となります。
- 現在の耐震基準に適合する工事(構造評点1.0以上)
- 京町家: 最大 300万円
- 木造住宅: 最大 200万円
- 土台や柱の修繕、劣化した土壁の塗り直しなどが含まれる
- 一定以上の耐震性能を確保する工事(構造評点0.7以上1.0未満)
- 京町家: 最大 150万円
- 木造住宅: 最大 100万円
- 耐震性能が従前よりも向上する工事(壁の設置や屋根の軽量化等)
- 京町家: 最大 100万円
- 木造住宅: 最大 80万円
防火・準防火地域に建物がある場合は、本格改修と合わせて防火改修を行うことが必須となります。また、同一の袋路(幅員4m未満の行き止まりの道)に接する2棟以上の京町家を同時に耐震改修する場合は、1棟あたり50万円が上乗せされる制度もあります(要件あり)。
簡易耐震改修工事への補助制度
簡易改修は、部分的な耐震性能の向上を目的とした工事で、屋根の軽量化の他に以下の工事が対象です。
- 屋根型
屋根の軽量化、屋根構面の強化(京町家最大60万円、木造住宅最大40万円) - 床型
2階床組の強化、小屋組の強化(京町家10万円、木造住宅5万円) - 壁型
金物の設置(木造住宅)、土壁の修繕(京町家)(京町家10万円、木造住宅5万円) - 足元型
土台、柱、基礎の劣化修繕、有筋の基礎の増設(木造住宅)、柱脚部の補強(京町家)(京町家10万円、木造住宅10万円)
簡易改修は、1住戸単位での申請が可能です。ただし、過去に同一内容で補助金を受けている場合は、今回の補助金額から減額されることがあります。
耐震シェルター等の設置
建物が倒壊しても命を守る空間を確保するため、部屋の中に頑丈なシェルターやベッドを設置する工事も補助対象です。
- 耐震シェルターの設置: 40万円。
- 耐震ベッドの設置: 40万円。
耐震シェルター等の設置は、本格改修のうち「現在の耐震基準に適合する工事(構造評点1.0以上)」以外の工事と併用が可能です。
防火改修
京都市では、地震時の火災対策として、以下の防火改修工事も補助対象としています。防火改修の対象地域は京都市内全域に拡大されました。
- 軒裏の防火改修
- 開口部の防火改修
- 木製防火雨戸の設置
- 長屋の界壁の防火改修
- 外壁の防火改修
また、震度5強以上の地震を感知し、自動でブレーカーを落とすことで通電火災を防止する感震ブレーカーの設置は5万円が補助されます。
防火改修は、本格改修と併せて行う場合は、京都市外の事業者が施工することも可能です。
京都市の屋根軽量化補助金に関するQ&A
京都市の屋根軽量化補助金に関するよくある質問とその回答をまとめました。
申請期間はいつからいつまでか
令和7年4月14日(月)から令和8年1月31日(土)までが申請期間です。
ただし、予算には限りがあるため、予算がなくなり次第、受付は終了となります。設計や工事に着手する前に、十分に期間に余裕を持って申請手続きを進めるようにしましょう。
リフォーム業者に指定はあるか
はい、指定があります。補助対象工事の施工者は、京都市内に本店または主たる事務所を置く事業者であることが条件です。 ただし、本格改修と併せて防火改修を行う場合は、この京都市内事業者の要件は適用されません。
他のリフォーム補助金との併用は可能か
京都市の「まちの匠・ぷらす」事業とあわせて、「京都安心すまい応援金」が利用できる場合があります。これは、未就学の子どもがいる世帯が既存住宅を購入してリフォームし居住する場合に、最大200万円の応援金を交付する制度です。
また、補助金によっては、過去に本補助金等(「まちの匠・ぷらす」以外の公的機関からの同種類似の補助金)の交付を受けている場合、今回の補助金額から減額されることがあります。詳細については京安心すまいセンターに確認することをお勧めします。
専門家への相談と京都市の公式問い合わせ先
補助金制度の利用には、専門的な知識が求められる場合があります。疑問点があれば、早めに専門家や京都市の窓口に相談しましょう。
京都市の相談窓口一覧
京都市では、京安心すまいセンターが補助金の受付だけでなく、耐震改修工事等に関する相談も受け付けています。
- 所在地: 〒600-8127 京都市下京区西木屋町通上ノ口上る梅湊町83番地の1(河原町五条下る東側)「ひと・まち交流館 京都」地下1階
- 電話: 075-744-1631(耐震・省エネ担当)
- FAX: 075-744-1637
- 開館時間: 午前9時30分~午後5時
- 休館日: 水曜・祝日・第3火曜および年末年始(12/29~1/4)
- アクセス:
- 市バス 4・7・205号系統「河原町正面」下車
- 京阪電車「清水五条」下車 徒歩8分
- 地下鉄烏丸線「五条」下車 徒歩10分
京安心すまいセンターでは、補助金の申請受付のほか、専門知識を持つ団体を紹介するなど、耐震改修工事等に関するさまざまな相談に応じていますので、お気軽にご連絡ください。また、無料の「耐震相談会」も実施されていますので、ぜひ活用を検討してください。
補助金申請サポートが可能なリフォーム会社
京安心すまいセンターは、補助金申請に関する相談や、専門知識を持つ団体の紹介を行っています。ご自身の状況に合わせて、これらの窓口を活用し、適切なリフォーム会社や専門家を見つけることをお勧めします。
まとめ
京都市の「まちの匠・ぷらす」事業は、木造住宅や京町家の屋根軽量化を含む耐震・防火改修を支援する貴重な制度です。屋根の軽量化は、地震時の建物の揺れを小さくし、倒壊のリスクを軽減する「命を守る最初の一歩」となる重要な工事です。
この補助金制度を活用することで、最大60万円 の補助金を受け取り、高額になりがちなリフォーム費用の負担を軽減できます。2025年度には制度の一部見直しも行われ、防火改修の対象地域が市内全域に拡大されるなど、より利用しやすくなっています。
申請期間は令和7年4月14日(月)から令和8年1月31日(土)まで ですが、予算がなくなり次第終了となるため、早めの情報収集と申請手続きが肝要です。自宅の耐震性に不安を感じている方は、まず京安心すまいセンターに相談し、この制度を上手に活用して、安心して暮らせる住環境を実現しましょう。